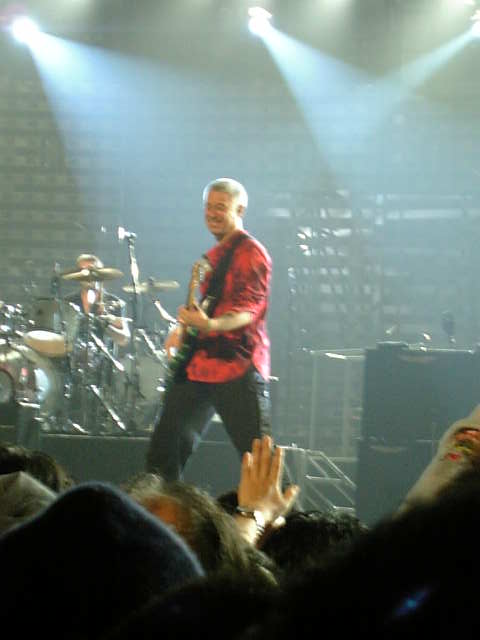「父親たちの星条旗」と「硫黄島からの手紙」を観た。
硫黄島という名前は知っていたが、深く歴史を学ばなかった僕にとっては教科書に出てくる
歴史上のキーワードの一つに過ぎず、こうしてクリント・イーストウッドが映画として
取り上げてくれなかったら、この先一生、この史実を知ることがなかったかもしれない。
あくまでも映画なので、ディテールなど細かく見ていけば誤りがあったりするのだろうが、
一つの戦闘が両側から公平な視点で描かれたことは画期的なことだと思う。
クリント・イーストウッドの作品に一貫して貫かれている精緻でストイックな描写は
この戦争の悲惨さを伝えるのにまさに打って付けだったのではないだろうか。
どちらも上映時間の長い作品だけど、その長さは感じなかった。
激しい戦闘シーンや残酷な殺戮シーン、主要人物の対話シーン、
後になって振り返ってみると、どれをとっても詩的な映像となって記憶に残っている。
しかしそれは映画の中身の良さというよりは、技法の問題なのかもしれない。
これまでに観てきた戦争映画を凌駕する作品だとは感じなかった。
とは言え、二作品とも優れた映画であることには異論がなく、
「硫黄島からの手紙」を撮ったクリント・イーストウッドには脱帽。
外国人が撮った作品でこれだけ日本人がきちんと描かれたのは初めてだろう。
それに、日本人には撮れなかった映画を撮ったという意味でも。
日本人の演技はそれぞれが印象深く素晴らしかった。
中でも嵐の二宮君は非常に頑張ったと思う。最後の表情も良かった。
映画の中では軽くしか触れられないが、どちらの国にも政治的な問題が見え隠れしている。
戦争で犠牲を強いられるのは市民であり、問題提起を行うこういった作品を作るのも市民。
政治家にこそ観てもらいたい作品だ。
今回の映画の主題とは直接関係ないのだが、「お国のために戦場に行って死んで来い」
「お国のためなら~」という無理強いで理不尽なことを押し付ける人たちの思考には
日本人のDNAとして空恐ろしいものを感じた。そして、ホリエモンに傾倒して、
モラルを無視してでもお金を儲けることを正当化する最近の若者に、ふとそのDNAを感じた。